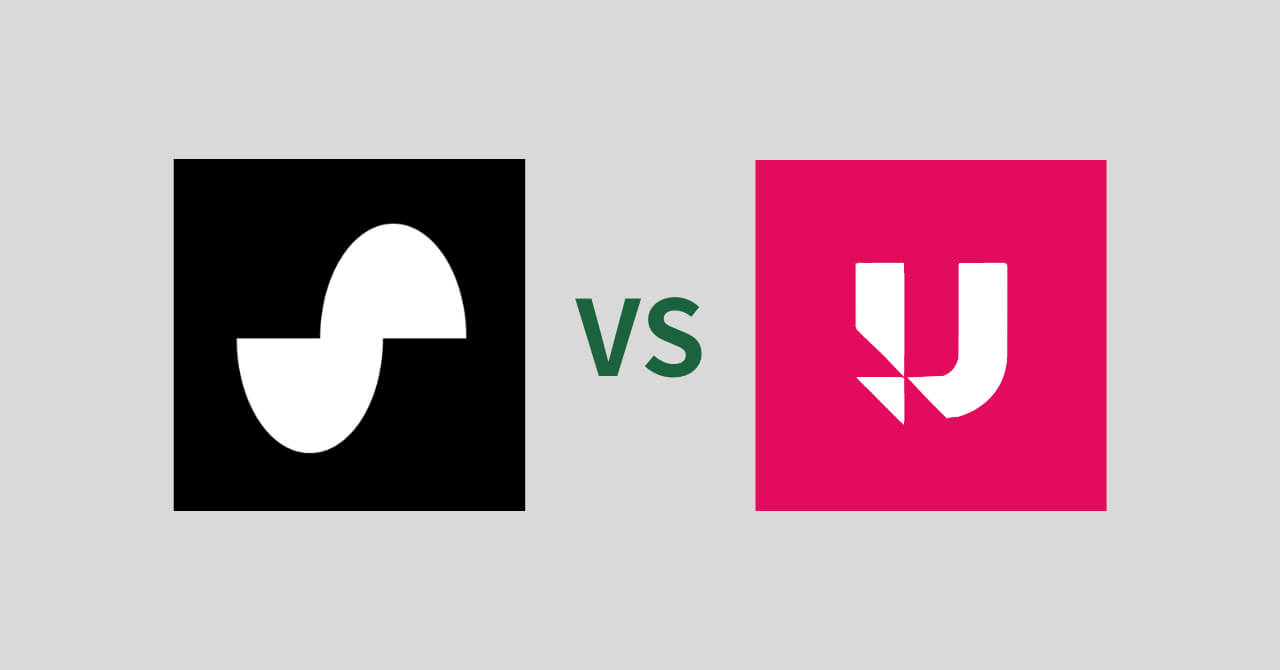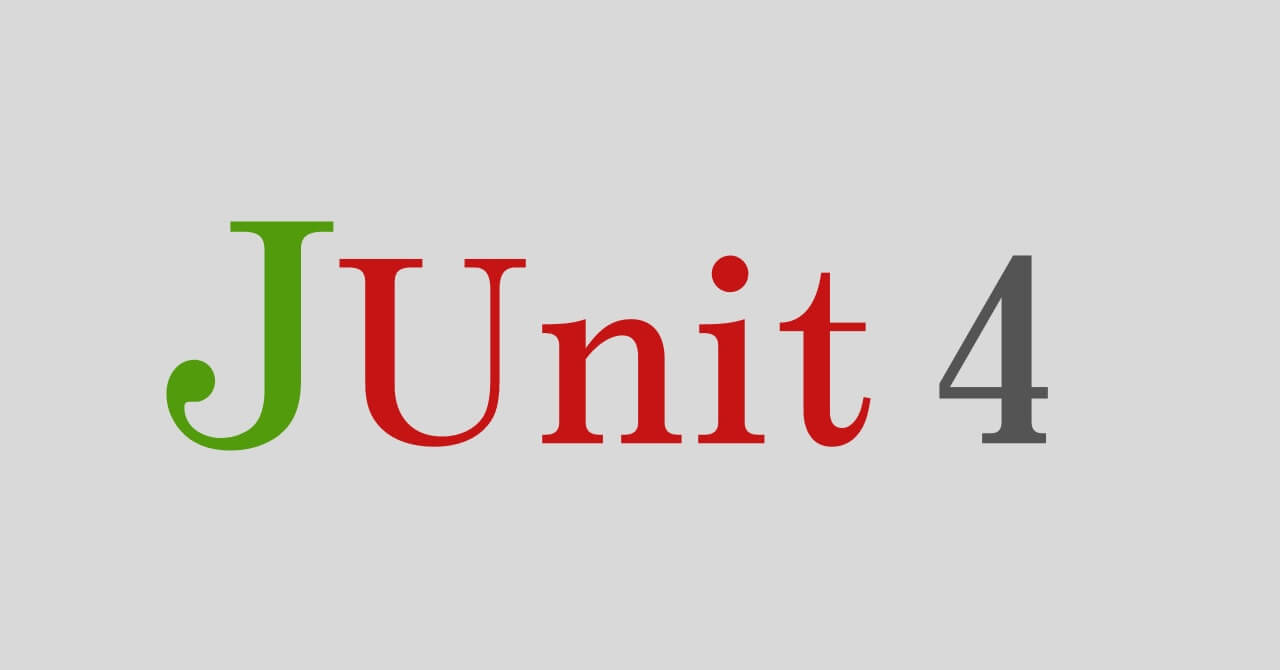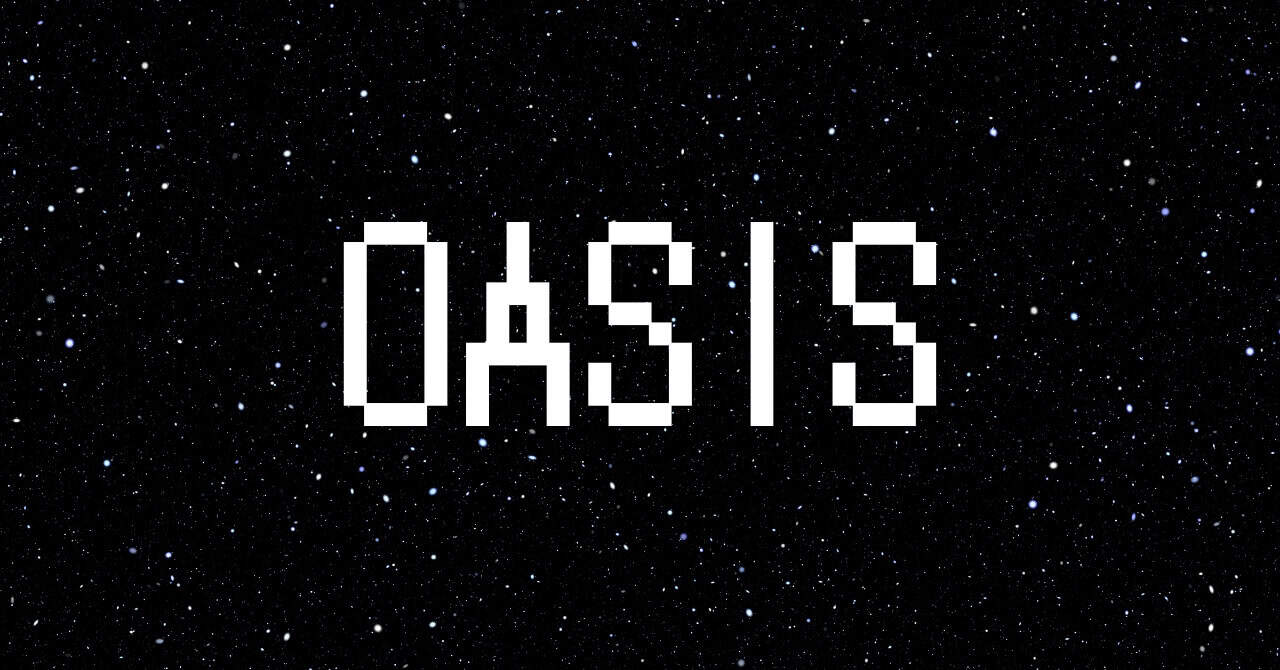AI Mac設定 Windows設定 WordPress おすすめアプリ おすすめガジェット お得情報 コピペで使える ブログ運営 ミニマリズム 中学生でもわかるIT 健康 問題解決 自動化 読書 転職先選び

「すべてがFになる」を20年ぶりに再読した。
1995年に書かれたこの小説は、今読んでも古さを感じない。むしろ、当時から現在のIT技術を予見していたかのような内容に驚かされる。
森博嗣は執筆当時、名古屋大学の助教授(現在の准教授)だった。専門は建築だが、研究室にはMacを配備し、小説は全てデジタルで執筆していたという。この背景が、作品に独特の技術的視点をもたらしている。
スマホは出てこないが、それ以外は現代そのもの
小説内では携帯電話は単語でのみしか出てこない。しかし、それ以外の技術描写は驚くほど現代的なのだ。
音声端末(現在のアレクサのような)、チャット、VR、食洗機、顔認証、これらは1995年当時、まだ一般には普及していない技術が当たり前のように出てくる。
特に印象的なのは、音声による家電制御の描写だ。現在のスマートホーム技術を彷彿とさせる内容が、20年以上前に書かれている。
プログラミングやIT技術が随所に登場
この小説の魅力は、IT技術者にとって身近な要素が随所に散りばめられていることだ。
プログラミングの話、データベースの話、ネットワークの話——これらが自然な形で物語に組み込まれている。特に、主人公の犀川創平が研究室でMacを使いこなす場面は、当時の大学のIT環境をリアルに描写している。
森博嗣自身がデジタル執筆を行っていたこともあり、技術的な描写に違和感がない。これは他の小説にはない特徴だ。
エンジニアが共感できる「論理的思考」の描写
主人公の犀川創平は、エンジニアが共感できるキャラクターだ。
論理的思考を重視し、感情的な判断を避ける。問題解決においては、データと事実を基に推理を進める。この思考プロセスは、プログラミングやシステム設計に携わる技術者にとって非常に親しみやすい。
「すべてがFになる」というタイトル自体も、プログラミングにおける変数の概念を想起させる。技術者にとっては、このタイトルからして興味を引かれる要素がある。
当時の大学のIT環境を垣間見られる
1995年当時の大学のIT環境が、リアルに描写されている。
研究室にMacが配備されていること、デジタルでの執筆作業、大学のネットワーク環境——これらは当時の最先端だった。現在のエンジニアにとっては、IT技術の歴史を学ぶ資料としても価値がある。
森博嗣が実際に体験していた環境だからこそ、描写に説得力があるのだ。
技術書とは違う「技術的思考」の学び
技術書では学べない「技術的思考」を、小説という形で学べるのがこの作品の魅力だ。
論理的な問題解決、データに基づく判断、感情に流されない思考——これらはエンジニアにとって重要なスキルだが、技術書ではなかなか学べない。
小説という形だからこそ、これらの思考プロセスを自然に理解できる。特に若手エンジニアにとっては、技術的思考の良いお手本になるだろう。
先見性に学ぶ「技術の本質を見抜く力」
森博嗣の先見性は驚くべきものだ。
VR、音声制御、センサー技術——これらは現在当たり前になった技術だが、1995年時点でこれらを小説に取り入れるのは並大抵のことではない。
この先見性は、技術の本質を見抜く力に支えられている。表面的な流行ではなく、技術の根本原理を理解していたからこそ、未来を予見できたのだ。
エンジニアにとって、この「本質を見抜く力」は非常に重要なスキルだ。
まとめ:エンジニア必読の技術小説
「すべてがFになる」は、エンジニアにとって特別な価値を持つ小説だ。
技術的な描写の正確さ、論理的思考の描写、先見性——これらは他の小説にはない特徴だ。特に、技術書では学べない「技術的思考」を小説という形で学べる点が貴重だ。
20年ぶりの再読で改めて感じたのは、この作品の先見性のすごさだ。現在のIT技術を予見していたかのような内容に、技術者としての森博嗣の眼力に驚かされる。
エンジニアなら一度は読んでおくべき作品だ。技術書とは違う角度から、技術的思考を学べる貴重な一冊だ。